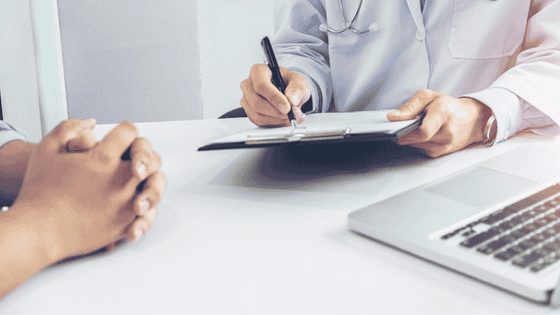年齢を重ねてからの妊娠を望む人は年々増えており、40代の方にとって不妊治療は大切な選択肢となっています。
ただし、不妊治療を受けたとしても必ず妊娠できるとは限りません。加齢とともに妊娠率は低下し、流産のリスクは高まることが分かっています。
不妊治療を考えている場合は、できるだけ早めに検査を受け、必要な治療を検討することが大切です。
本記事では、40代における妊娠率・流産率、妊娠を妨げる主な要因について解説します。加齢による体の変化について理解を深め、今後の選択を考える参考にしてください。
40代で不妊治療を受けた場合の妊娠率と流産率は?
40代になると、妊娠に至る確率は大きく低下し、流産のリスクも上昇します。生殖補助医療(ART)を行う場合でも、加齢の影響は避けられません。
日本産科婦人科学会が発表した「2023年 体外受精・胚移植等の臨床実施成績」によると、体外受精や顕微授精などの生殖補助医療における妊娠率・流産率は以下のとおりです。
<2023年 体外受精・胚移植等の臨床実施成績(40〜49歳を抜粋)1)>
表を見ると、40歳で生殖補助医療を行った場合の妊娠率は17.2%です。しかし、45歳では4.2%、49歳では2.0%にまで下がります。40歳代においては年齢が上がるにつれて、妊娠率は大きく低下していく傾向があります。
流産率も40歳を過ぎると30〜50%にまでのぼります。年齢が高くなるほど、妊娠しにくいだけでなく、妊娠を維持することも難しくなるのです。
40代で不妊治療を受けている人の割合
日本産科婦人科学会の「2023年 体外受精・胚移植等の臨床実施成績」によると、体外受精や顕微授精などの生殖補助医療の実施数は、561,664周期でした。そのうち40〜49歳の女性による治療は204,851周期であり、全体の約36.5%を占めています1)。生殖補助医療を受けている人のうち、およそ3人に1人が40代という計算になります。
晩婚化・晩産化を背景に不妊治療を受ける人は増えています。特に40代で妊娠を望む人にとって、不妊治療は重要な選択肢となっています。
ただし、1歳ごとに妊娠率が大きく低下することを踏まえると、できるだけ早く治療をはじめることが重要です。
40代の不妊治療で妊娠を妨げる要因
40代では、体のさまざまな変化によって妊娠しにくくなります。不妊治療においても加齢の影響は避けられません。
妊娠を妨げる要因には、主に以下5つが挙げられます。
- 卵子数が減少する
- 卵子の質が低下する
- 染色体異常が生じやすくなる
- 婦人科系の病気を発症しやすくなる
女性は卵子の状態や婦人科系の病気により、妊孕性(にんようせい:妊娠する力)が低下します。
また、男性側にも加齢が妊娠を妨げることがあります。加齢により、精子の量や質が低下することで、妊娠しにくくなることがあります。
卵子の数が減少する
40代になると、体内に残る卵子の数が少なくなります。卵子のもとになる卵母細胞は、生まれた後新たにつくられず、特に30代後半〜40代にかけて急速に減少していくためです2)。
卵巣に残っている卵子の数が少ない場合、自然妊娠が難しいだけではありません。不妊治療においても、採卵時に得られる卵子数が限られ、治療が難しくなる場合があります。
なお、卵巣に残る卵子数はAMH値によって推測され、不妊治療を検討する上で重要な目安となっています。
AMHについては以下のページで詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。
関連ページ:AMH
卵子の質が低下する
卵子の数だけでなく、卵子の質も妊娠を妨げる要因です。「質」とは、卵子そのものの健康状態を指します。
卵子の質が低いと、胚の発育や受精・着床がうまく進まなくなることがあります。たとえ卵子の数が多く残っていても、質が低ければ妊娠の可能性は下がってしまうのです。
卵子の質が低下する詳しいメカニズムは解明されていませんが、染色体異常や細胞の機能低下、DNAの異常が関係していると考えられています。
現時点で、医学的に証明された卵子の質を上げる方法はなく、卵子凍結のみが加齢の影響を確実に防ぐ手段となっています。
染色体異常が生じやすくなる
卵子の質が低下すると染色体異常を持つ卵子が増え、さらに妊娠は成立しにくくなります。
卵母細胞は排卵されるまでの数十年間、細胞分裂を止めたまま体内にとどまります。この長い期間に細胞の老化が進み、染色体の数や構造に異常を持つ卵子が増えてしまうのです。
日本受精着床学会によると、受精後5日間培養した胚に染色体異常がみられる割合は、20代で約25%、44歳では約90%にのぼると示されています3)。
また、染色体異常は不妊の原因になるだけでなく、流産のリスクも高めることが分かっています2)。
婦人科系の病気を発症しやすくなる
年齢を重ねると、子宮や卵巣の働きにも変化が起こりやすくなり、婦人科系の病気にかかるリスクが高まります。なかには妊娠に影響を及ぼす病気もあるため注意が必要です。
以下は、妊娠に影響する婦人科系疾患の一例です。
特に30〜40代以降は婦人科系の病気を発症しやすくなります。妊娠を望む場合は病気にかかるリスクも踏まえた対策を考えることが大切です。
精子の量・質が低下する
妊娠を妨げる原因は、女性だけではなく男性側にもあります。特に精子の状態は妊孕性に大きく影響します。
以下は、精子の状態を左右する主な要素です。
- 精液量
- 精子の濃度
- 精子の運動率(活発に動く割合)
- 精子の質(染色体やDNAの状態など)
これらはいずれも加齢とともに徐々に低下していきます。
精液量は年齢と共に減少し、それに伴い精子の数も少なくなると考えられています。また、動きも弱くなり、運動率は5年ごとに1.2%ずつ下がるとの報告もあります4)。
精子の質そのものも30代後半から低下していくと考えられており、40代の不妊治療において加齢の影響は避けられません。生殖補助医療について調べた海外の研究では、40歳以上の男性の妊娠率は、35歳未満に比べて低い結果であり、統計学的に差があったという報告もあります5)。
不妊の原因は男女両方に存在するため、パートナーと一緒に検査や治療を受けることが重要です。
40代からはじめる不妊治療の流れ
一般的に不妊治療は、タイミング療法からはじめ、妊娠に至らない場合に人工授精・体外受精(c-IVF)および顕微授精(ICSI)へとステップアップしていきます。
ただし40代の場合は、年齢を考慮して、ステップアップする時期を早めたり、はじめから生殖補助医療が推奨されることもあります。
<不妊治療>
- タイミング療法:排卵に合わせて性交渉を持つ方法
- 人工授精:精子を子宮内に注入する方法
- 体外受精:卵子と精子を体外で受精させる方法
- 顕微授精:精子を卵子に直接注入する方法
タイミング療法
タイミング療法は、排卵日を予測し、性交のタイミングを合わせる方法です。超音波検査や尿検査で排卵日を予測し、性交渉の時期を医師が指導します。
最も自然な方法に近く、体への負担が少ないのが特徴です。ただし、女性が40歳以上の場合は自然妊娠が難しいケースを踏まえ、早めのステップアップが推奨されることもあります。
タイミング療法については、以下のページで詳しく解説しているのであわせてご覧ください。
関連ページ:タイミング療法
人工授精
人工授精は、採取した精液から動きの良い精子を選別し、排卵のタイミングに合わせて子宮内に直接注入する方法です。精子の異常が軽度の場合や、性交渉が難しい場合などに適応されます。
人工授精も比較的体への負担が少ない治療です。4〜6回実施しても妊娠しない場合はステップアップの目安となりますが、年齢や状況に応じて3〜4回、もしくはさらに早い段階でも生殖医療への移行が検討される場合があります。
人工授精については、以下のページで詳しく解説しているのであわせてご覧ください。
関連ページ:人工授精
体外受精・顕微授精
体外受精や顕微授精は、より専門的な治療である生殖補助医療に分類されます。
顕微授精は、体外受精のひとつであり、通常の体外受精では受精が難しい場合に行われます。
年齢が上がると一度の採卵で得られる卵子の数が少なくなり、質の良い卵子も得られにくくなります。また、移植時に母体年齢が高いと、その影響で妊娠率が下がることもあります。
40代でも妊娠は可能ですが、生殖補助医療は年齢を考慮して早めの相談・対応が求められます。妊娠を望む場合、まずは検査によって体の状態を知り、結果をもとに今後の方針について専門医からアドバイスを受けましょう。
体外受精・顕微授精ついては、以下のページで詳しく解説しているのであわせてご覧ください。
不妊治療の保険適用と費用について
2022年4月から、それまでは自費診療で行われていた不妊治療や不妊検査の一部が保険適用となり、経済的な負担が軽減されるようになりました。
実際にかかる費用は、治療の内容や使用する薬剤、通院回数などによって異なります。特に生殖補助医療の費用は、採卵数や凍結保存する胚の数によって大きく変動します。
保険適用になる条件については、以下のとおりです。
- 一般不妊治療(タイミング法、人工授精):年齢・回数の制限はなし
- 生殖補助医療(体外受精、顕微授精など):年齢・回数の制限あり
<年齢・回数の条件(生殖補助医療)6)>
43歳以降に治療を開始した場合は、自費診療となります。また、通算の胚移植の回数が上記の回数制限を超えた場合も、保険は適用されません。
実際に治療を受ける際は、これらの条件を十分に確認しましょう。
不妊治療にかかる費用は実施する治療法や通院する回数、使用する薬剤などによっても大きく異なります。目安としては治療一回あたりでタイミング療法は10,000円程度、人工授精では10,000〜20,000円程度です。
体外受精では、採卵の数や受精卵の培養数、培養日数、胚移植の方法、凍結保存の数などでも変わります。体外受精の1周期あたりの総額は、100,000円以下〜200,000円程度が目安となります。なお、高額療養費制度の対象となる場合もあります。
不妊治療の保険適用や費用については、以下の記事でも解説しているのであわせてご覧ください。
関連記事:不妊治療の保険適用はどこまでできる?条件や費用についても解説
40代の不妊治療で利用できる助成金はある?
自治体などの助成金は年齢制限があることが一般的です。
40代では利用できる助成金も限られますが、中には条件付きで申請できるものもあるため、確認してみるのがよいでしょう。
例として、東京都の不妊治療に関わる主な助成金の制度は以下のようになっています。
上記のとおり、「特定不妊治療費(先進医療)助成事業」に関しては、年齢の条件が43歳未満であれば対象になる場合があります。ご自身の状況に合わせて活用できる場合は検討しましょう。
40代の不妊治療に関してよくある質問
ここからは、40代の不妊治療に関してよくある質問にお答えします。
Q:40代で不妊治療をはじめるのは遅いですか?
40代で不妊治療をはじめる人も珍しくはありません。ただし、できるだけ早く治療を開始することが求められます。
年齢とともに妊娠しにくくなるだけでなく、たとえ妊娠できたとしても高齢の妊娠では多くのリスクを伴うためです。
お母さんは妊娠合併症や分娩時のトラブルが生じやすくなり、赤ちゃんも先天的な病気の発症リスクが高まります。また、早産や流産のリスクも高まることが分かっています。
不妊治療を検討している場合、まずは専門医に相談し、望ましい治療についてアドバイスを受けましょう。
Q:40代で不妊治療するとダウン症や障害児が生まれるリスクはある?
40代での妊娠は、20〜30代に比べダウン症などの先天的な病気のリスクが高まるとされています。これは不妊治療自体が原因ではなく、加齢によって染色体異常が起こりやすくなるためです。

厚生労働省.「不妊に悩む方への特定治療支援事業等のあり方に関する検討会」報告書を参考に作成
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11908000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Boshihokenka/0000016944.pdf
ダウン症を含む染色体異常の主な要因は、母親の加齢です。高齢になるほど、ダウン症や染色体異常の赤ちゃんが生まれるリスクは上昇します。たとえば母親が25歳の場合、ダウン症の発生率は1250分の1ですが、40歳では106分の1となり、年齢と比例して確率が上昇します10)。
40代で不妊治療を検討する際は、加齢によるリスクを正しく理解した上で治療することが大切です。専門医とよく話し合って進めるようにしましょう。
Q:40代の妊活・不妊治療は何から始めたらいいですか?
40代で妊娠を望む場合、まずは体の状態を把握することからはじめましょう。ひとつの選択肢としてブライダルチェックがあります。
ブライダルチェックは、婦人科や不妊専門クリニックで受けられる検査で、妊娠に向けて体に異常がないか確認します。
<ブライダルチェックでわかること>
- 子宮や卵巣に異常はないか
- 妊孕性に問題はないか
- 妊娠・出産に影響する病気はないか
女性では、血液検査や超音波検査などにより、子宮・卵巣の状態やホルモン値、卵巣予備能などを調べます。男性では血液検査や精液検査を行い精子の状態を評価します。
40代のカップルでは、お互いに不妊の原因を持つケースが少なくありません。ブライダルチェックは、妊娠に向けた準備としてだけでなく、病気の早期発見や将来の健康管理にもつながります。
トーチクリニックでは男女それぞれのブライダルチェックに対応しています。結婚の予定に関わらず提供していますので、気軽にご相談ください。
ブライダルチェックについての詳しい内容は、以下の記事をご覧ください。
おわりに
参考文献
1)日本産科婦人科学会. 2023年 体外受精・胚移植等の臨床実施成績. 日本産科婦人科学会ウェブサイト.
https://www.jsog.or.jp/activity/art/2023_JSOG-ART.pdf
2)厚生労働省 令和3年度子ども・子育て支援推進調査研究事業. 治療の難しい不妊症のためのガイドブック. 厚生労働省ウェブサイト.
https://www.gynecology-htu.jp/refractory/dl/hunin_guidebook.pdf
3)日本生殖医学会. Q10. 卵子の質、胚の質とはどういう意味ですか? 日本生殖医学会ウェブサイト.
http://www.jsfi.jp/citizen/art-qa10.html
4)日本生殖医学会. Q25. 男性の加齢は不妊症・流産にどんな影響を与えるのですか? 日本生殖医学会ウェブサイト.
http://www.jsrm.or.jp/public/funinsho_qa25.html
5)Lu XM, Liu YB, Zhang DD, Cao X, Zhang TC, Liu M, Shi HJ, Dong X, Liu SY. Effect of advanced paternal age on reproductive outcomes in IVF cycles of non-male-factor infertility: a retrospective cohort study. Asian J Androl. 2023;25(2):245-251.
https://journals.lww.com/ajandrology/fulltext/2023/25020/effect_of_advanced_paternal_age_on_reproductive.15.aspx
6)こども家庭庁. 不妊治療に関する取組. こども家庭庁ウェブサイト
https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/funin
7)東京都福祉局. 不妊検査等助成事業の概要. 東京都福祉局ウェブサイト
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/shussan/funinkensa/gaiyou
8)東京都福祉局. 東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の概要. 東京都福祉局ウェブサイト
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/josei/funin-senshiniryou/gaiyou
9)東京都福祉局. 卵子凍結に係る費用の助成 事業の概要. 東京都福祉局ウェブサイト
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/shussan/ranshitouketsu/touketsu/gaiyou
10)厚生労働省.「不妊に悩む方への特定治療支援事業等のあり方に関する検討会」報告書. 厚生労働省ウェブサイト
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11908000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Boshihokenka/0000016944.pdf