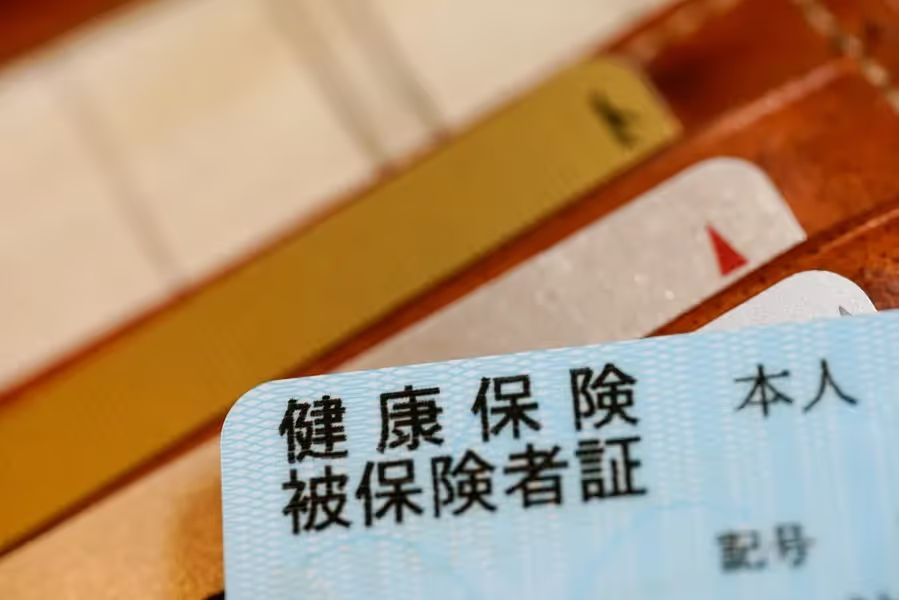人工授精や体外受精などの不妊治療が保険適用となり、治療を前向きに検討する方が増えています。この記事では、不妊治療の保険適用について対象となる治療項目、年齢・回数制限などの条件、メリット・デメリット、自治体による助成制度や医療費控除についてを詳しく解説します。
2022年4月より不妊治療も保険適用の対象に
2022年4月より、不妊治療のうち、「一般不妊治療(タイミング療法・人工授精)」と「生殖補助医療(体外受精・顕微授精・胚移植など)」の基本的な診療が保険適用の対象になり、原則3割負担で治療が受けられるようになりました。またタイムラプス培養などの「先進医療」と位置づけられる追加の治療そのものは保険適用外であるものの、保険診療と併用が可能です1)。
これまで不妊治療は、原因を調べる検査とその疾患の治療に限って保険適用となっていたため、高額な治療費がかかっていました。
保険適用の対象が広がったことで、子どもを望む方の経済的負担の軽減につながり、選択肢が増えることが期待されています。
保険適用になった治療項目
2022年4月より新たに保険適用となった治療項目はタイミング療法と人工授精を指す「一般不妊治療」と体外受精を指す「生殖補助医療(ART)」です1)。
一般不妊治療を行っても妊娠に至らない場合に、生殖補助医療へステップアップするのが一般的な流れです。しかし、原因や年齢などの状況によっては早い段階から生殖補助医療を行う場合もあります。
保険適用になった治療項目について、治療内容や平均的な費用を詳しく解説します。
一般不妊治療
一般不妊治療は、排卵日を予測し性交のタイミングを合わせる「タイミング療法」と、精液を子宮の中に注入する「人工授精」の2種類があります。
体への負担が比較的少なく、より自然な妊娠に近い形で行う不妊治療です。保険適用に年齢・回数制限はありません。
タイミング療法
タイミング療法は、経腟超音波検査などで排卵時期を予測して、性交渉の時期を医師が指導する治療法で、身体的・経済的負担が少ないのが特徴です。
費用は保険適用の場合、1周期あたり1万円程度が目安となります。通院の回数のほか、検査の回数や検査の内容、排卵の確実性やタイミングを合わせやすくするために使用する排卵誘発剤の使用の有無、使用する薬剤の種類によっても費用が変わります。
タイミング療法については、以下のページで詳しく解説しているのであわせてご覧ください。
関連ページ:タイミング療法
人工授精
人工授精は主に、乏精子症や精子無力症などの男性不妊症に対して行われます。
マスターベーションなどによって採取した精液から運動性の良い精子を取り出し、排卵の時期にあわせてカテーテル(細い管)を用いて子宮内に注入します。
妊娠率は1周期あたり約5〜10%、排卵誘発剤を使用した場合は約10〜15%といわれています2)。
人工授精そのものの費用は、国の診療報酬で定められた点数が1,820点(2025年時点)であり3)、健康保険の適用で3割負担だと5,460円です。タイミング療法と同様に事前の診察や検査、使用する薬の費用なども考慮すると、保険適用で1周期あたり1〜2万円程度が目安となります。
人工授精については、以下のページで詳しく解説しているのであわせてご覧ください。
関連ページ:人工授精
生殖補助医療
生殖補助医療は、採卵や受精によって得た卵子や精子を体外で受精させる「体外受精」「顕微授精」、受精卵(胚)を体外で培養したあとに子宮内に移植する「胚移植」などの治療法があります。
生殖補助医療の治療の流れは、以下のとおりです。
- 採卵
- 体外受精または顕微受精
- 受精卵(胚)培養、胚凍結保存
- 胚移植
採卵
採卵は、経腟超音波検査で観察しながら卵胞に針を刺して、卵胞液とともに卵子を吸引する「経腟的採卵」が一般的です。
子宮内膜症や子宮腺筋症などの癒着がある場合、腫瘍がある場合などは、腹部から卵子を取り出す「経腹的採卵」が選択されることもあります。
採卵時に麻酔を行うかどうかは、予測される採卵数や採卵の困難さに応じて決定されます。
費用は採卵する卵子の個数によっても変わります。採卵の費用は、採卵術の保険点数(3,200点)と採卵の数に応じた分の費用が加算されます。
例として、3個採卵した場合は2〜5個までの3,600点が加算されるため合計で6,800点3)、健康保険の適用で3割負担だと20,400円となります。
体外受精
体外受精は、採卵により得た卵子と精子を体外で受精させる方法です。卵子と精子を同じ培養液に入れ、精子自らの力で受精させる自然に近い方法です。
体外受精そのものの費用は、国の診療報酬で定められた点数が3,200点(2025年時点)であり3)、健康保険の適用で3割負担だと9,600円です。
顕微授精
顕微授精は、顕微鏡下で細いガラスの針を用い、精子の運動性や形態から選択された良質な精子を1匹だけ採取して、卵子に入れることにより受精を目指す方法です。
原則、精子の数が少ないなどの男性不妊や受精障害など、この治療法でないと受精が難しい場合に行われます。
顕微授精そのものの費用は、以下の表のとおり個数によって異なります3)。
受精卵(胚)培養
受精卵(胚)培養は、体外受精あるいは顕微受精でできた受精卵※1 を、子宮に移植可能な状態(胚※2)になるまで、体内の環境にできるだけ近く調整された環境下で育てる方法です。受精卵培養は、通常採卵後から3〜6日間行われます。
※1 受精卵:卵子と精子が結合したばかりの卵子
※2 胚:細胞分裂がはじまった受精卵
卵子・精子の質や環境によって、途中で細胞分裂が止まってしまうことも少なくありません。培養の過程で胚の質を評価し、移植に適した胚を選別します。
受精卵・胚培養そのものの費用は、以下のとおりです3)。
※3 胚盤胞:採卵から5~6日間培養した受精卵
胚凍結保存
胚凍結保存とは、体外受精や顕微授精でできた受精卵を凍らせて保存しておく方法です。
採卵術によって受精卵が複数個得られた場合、これを凍結保存しておくことで、再度採卵をすることなく胚移植が可能となります。また、将来の兄弟姉妹を迎えることも期待できます。
凍結保存の方法として、細胞内の水分を排出したあとに凍結保護剤を浸透させ、液体窒素(-196℃)内に投入する「超急速ガラス化法」が一般的です。
この方法の融解後の受精卵の生存率は95%以上とされています4)。-196℃という低温環境では生物の活動や化学反応がほとんど止まるため、受精卵の保存が可能となります。
胚凍結保存の費用は以下のとおりです3)。
胚移植
胚移植は、腟に細いチューブを挿入して培養した胚を子宮に戻す処置です。移植する時期による分類では、「新鮮胚移植」と「凍結融解胚移植」の2種類があります。
それぞれの方法や主なメリットについては表のとおりです。
なお、生殖補助医療で移植する胚は、多胎妊娠(双子や三つ子など)を防止する目的で、原則として単一とする旨が日本産科婦人科学会の見解として公表されています5)。連続して妊娠できなかった場合や年齢などを考慮した例外を除き、基本は1個の胚を移植することになります。
胚移植の費用は以下のとおりです3)。
保険適用になる条件
不妊治療の保険適用の対象は広がりましたが、すべてが対象となるわけではありません。年齢や回数に制限があることを理解しておきましょう。
ここでは、不妊治療の保険適用の年齢・回数制限や、回数のカウントがリセットされる基準について解説します。
年齢・回数制限
一般不妊治療の保険適用には年齢・回数制限はありませんが、生殖補助医療の場合は以下の表のとおり制限があります。
42歳で不妊治療を開始し治療期間中に43歳になった場合は、その周期の胚移植までが保険適用となります。
43歳未満という年齢制限が定められている理由は主に以下の点があげられます。
- 妊産婦の死亡率が高くなる
- 生殖補助医療の出産率が下がり、流産率が上がる
- 妊娠高血圧症候群などの合併症のリスクが高くなる
- 周産期(出産前後)の赤ちゃんの死亡率が高くなる
回数の数え方とリセットの基準
不妊治療の保険適用における回数の数え方は、採卵から胚移植までの一連の周期を「1回」とします。胚移植を実施した時点で1回としてカウントされることを理解しておきましょう。
また、保険適用の回数は1子ごとの条件であり、無事に出産に至った場合や12週を超えて死産になった場合は保険適用の回数がリセットされます。
事実婚も対象
法律上の夫婦だけでなく、事実婚のカップルも保険適用の対象です。
事実婚の場合は、以下3点の条件が必要となります6)。
- 重婚でない(両者がそれぞれ他人と法律婚でない)
- 同一世帯である(同一世帯でない場合には、その理由について確認する)
- 治療の結果、出生した子について認知を行う意向がある
医療機関を受診した際に事実婚関係について確認されたり、書類を求められたりする場合があります。提出書類については、クリニックや自治体によっても異なる可能性があるため、それぞれの窓口で確認するようにしましょう。
保険適用になったメリット・デメリット
不妊治療が保険適用になったことで経済的負担が減り、治療を前向きに検討される方が増えました。ただし、従来の「特定不妊治療助成制度」が廃止されたため、結果的に自己負担額が増える場合もあります。
保険適用になったことによるメリット・デメリットについては表のとおりです。
上記のように経済的な負担が軽減され、高額療養費制度も利用できる場合がある点、統一した基準で治療が受けられる点など一般的には保険適用でのメリットが大きいといえます。
一方で、保険適用ではない個別の治療を併せて実施する場合は、混合診療に該当し全額自費となります。また、保険適用にも年齢や回数の条件があることは特に注意したい点です。
不妊治療の保険適用のメリットやデメリットについて、以下の記事でも詳しくまとめているのであわせてご覧ください。
関連記事:不妊治療を保険適用で受けるデメリットとは?費用負担を減らす制度も解説
不妊治療を受ける上での注意点
不妊治療を受ける前に確認しておきたい、自治体による助成金や、医療費控除について解説します。申請期限が設けられている制度もあるため、よく理解した上で治療を始めましょう。
各自治体の助成金制度を確認
不妊治療が保険適用になりましたが、自治体によってはそれとは別に助成金制度が設けられているところもあります。
例えば、医療保険が適用となる生殖補助医療(体外受精・顕微授精)と併用して実施される先進医療に対して、治療費の自己負担額の一部を助成するケースがあります。
ただし、先進医療として厚生労働大臣に認められた不妊治療であることや、実施医療機関として指定を受けている医療機関であることなど条件もあるため、要件を確認したうえで申請しましょう。
【例】東京都の場合
都内在住者を対象に「特定不妊治療費(先進医療)助成事業」を実施しており、特定不妊治療(保険診療)と併せて実施した「先進医療に係る費用」が助成されます7)。
先進医療にかかった費用の10分の7について、15万円が助成額の上限となっています。
例えば1回の治療で先進医療を実施し、計10万円かかった場合は助成額は7万円となります。
申請期限は「1回の治療」が終了した日の属する年度末3月31日(電子申請送信日・消印有効)までになっているため注意が必要です。
また東京都の場合、市区町村によっては東京都の助成に上乗せし、独自の助成制度を設けているところもあります。お住まいの地域の自治体に助成制度があるかどうか、その内容についてはそれぞれホームページなどで確認しましょう。
医療費控除を受ける際は正しく申告
不妊症の治療にかかった費用は、医療費控除の対象になります8)。
医療費控除とは支払った医療費が一定額を超える時に、計算される金額の所得控除を受けることができる国が定めている制度です。
正確に申請するためにも、受診時の領収書は必ず保管しておきましょう。また、自治体の助成金制度や民間保険を利用した場合は、受給した金額を差し引いて申請する必要があるため注意しましょう。
不妊治療の保険適用などに関してよくある質問
不妊治療の保険適用などについて、多くの方が抱く疑問にお答えします。
Q:体外受精の一連の治療費は保険適用でいくらになる?
体外受精の一連の治療でかかる金額は、治療の内容によって大きく異なります。
1周期あたりの総額は、100,000円以下〜200,000円程度が目安となります。
採卵の数や受精卵の培養数や培養日数、胚移植の方法、凍結保存の数などで保険点数が変わってきます。そのほかにも検査の回数や使用する薬剤などによっても金額が変わる可能性があります。
Q:不妊治療の助成金制度はなくなった?
不妊治療の保険適用により国の「特定不妊治療費助成制度」は2022年4月で廃止されました。
しかし、自治体によっては独自の助成制度があるところもあるため、お住まいの自治体のホームページなどを確認しましょう。
例として、医療保険が適用となる生殖補助医療(体外受精・顕微授精)と併用して実施される先進医療に対して、治療費の自己負担額の一部を助成するケースなどがあります。
Q:不妊治療の保険適用は6回以上だとどうなりますか?
不妊治療の中でも、タイミング法や人工授精などの一般不妊治療は回数制限はありません。
一方で生殖補助医療を受ける場合は、保険適用となる回数の上限が決まっています。女性が40歳未満の場合は1子ごとに6回までが上限であり、それ以降は原則自費診療となります。
Q:不妊治療の保険適用は43歳以上だとどうなりますか?
生殖補助医療(体外受精・顕微授精)を受ける場合、43歳以上は保険適用の年齢上限を超えるため、原則は自費診療となります。
年齢を考慮した上で、自費診療でも実際に不妊治療を実施するかは医療機関と相談する必要があるため、現在の状況や希望などを医療機関側としっかり話し合うようにしましょう。
おわりに
参考文献
1)こども家庭庁.不妊治療に関する取組.こども家庭庁ウェブサイト.
https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/funin
2)一般社団法人 日本生殖医学会.生殖医療Q&A.Q10.人工授精とはどういう治療ですか?.日本生殖医学会ウェブサイト.
http://www.jsrm.or.jp/public/funinsho_qa10.html
3)厚生労働省. 診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 令和6年 厚生労働省告示第57号 別表第一(医科点数表). 厚生労働省ウェブサイト.
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001251499.pdf
4)Tummon IS, Wentworth MA, Thornhill AR. Frozen-thawed embryo transfer and live birth: Long-term follow-up after one oocyte retrieval. Fertil Steril. 2006;86(1):239–242.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0015028206005528
5)日本産科婦人科学会. 生殖補助医療における多胎妊娠防止に関する見解. 日本産科婦人科学会ウェブサイト
https://fa.kyorin.co.jp/jsog/readPDF.php?file=77/8/077081014.pdf#page=14
6)厚生労働省. 事務連絡 令和4年3月16日 不妊治療に係る診療報酬上の取扱いについて. 厚生労働省ウェブサイト
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000913723.pdf
7)東京都.福祉局.東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の概要.東京都ウェブサイト.
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/josei/funin-senshiniryou/gaiyou
8)国税庁.所得税.不妊症の治療費・人工授精の費用.国税庁ウェブサイト.
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/37.htm