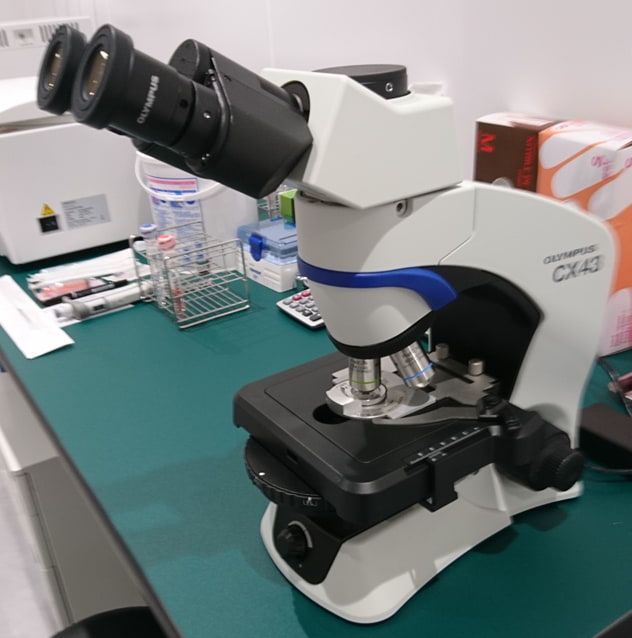精子凍結とは、後に用いるために採取した精子を凍結しておく不妊治療です。不妊治療当日に夫(パートナー)が不在となるときや、病気治療により妊孕性(にんようせい:妊娠する力)の低下が予測されるケースなどが対象です。基本的に治療は保険の適用外ですが、医療上必要があると認められれば、保険診療の対象となることもあります。
精子凍結とは
精子凍結とは、採取した精子を凍結・保存する不妊治療のひとつです。採取した精子は、-196℃の液体窒素で冷却し凍結します。凍結保存するため、長期にわたって保存できます。医学的にも有効性が認められた治療です。
精子凍結の流れと方法
精子凍結は、採精・精子凍結の流れで行われます。治療当日に融解され、人工授精や体外受精、顕微授精に用いられます。融解までの流れは以下のとおりです。
- 採精:精子を凍結する日に、自宅または医療機関で精液を採取します。採取した精液は、精液量や精子濃度、精子運動率といった検査が行われます。
- 精子凍結:採取された精液から質のよい精子が選ばれ、洗浄・濃縮されます。凍結保存液と混ぜ、凍結保存専用容器に入れ、-196℃の液体窒素タンクで保存します。
- 融解:治療の当日は、医療機関のスタッフが凍結精子を取り出し、ゆっくりと融解します。
精子凍結の対象と目的
精子凍結は、子どもを望むすべての方が対象になります。年齢の明確な定めはありませんが、一般的には生殖年齢が対象とされており、その基準は医療機関によって異なります。
精子凍結を行う目的は、主に以下の3つです。
- 夫が長期出張中の場合
- 精子が少ない・質がよくない場合
- 抗がん剤や放射線治療前における妊孕性の温存
ひとつずつ詳しく解説します。
夫が長期出張中である場合
人工授精などの治療を受ける日に、夫が不在の場合もあります。たとえば、出張や海外赴任中のときです。治療当日には精子を採取できないため、事前に精子を採取し、凍結保存します。治療当日に溶解すれば、人工授精や体外受精が可能になります。
精子が少ない・質がよくない場合
精子凍結は、将来の不妊治療に備えて行うことがあります。精子が少なかったり、質がよくなかったりする際、集められるときに精子を採取しておき、将来の妊娠に向けて保存しておくという選択肢になります。
トーチクリニックでは精液の状態を調べる精液検査も実施しています。
精液検査について、詳しい内容を確認したい場合は下記のページをご覧ください。
抗がん剤や放射線治療前における妊孕性温存
がんや白血病といった病気の治療により、将来的な妊孕性が低くなると考えられるケースは、精子凍結の対象になります。
抗がん剤や放射線の治療を受けると、がん細胞だけでなく、正常な細胞にまでダメージが加わります。その場合、生殖機能に影響を及ぼし、不妊の原因となる可能性があります。この場合の精子凍結は、生殖機能が低下する前に状態のよい精子を保存するために行います。
将来子どもを望む場合、精子凍結をしておけば、治療が始まった後の妊娠で凍結した精子を使用できます。
精子凍結にかかる費用と更新
精子凍結の費用は基本的に保険適用外ですが、医療的に必要があると認められた際は、保険診療の適用1)になります。
選定療養(自費診療)の対象となるのは、医療上必要があると認められない場合や、患者さんの希望で行われる場合です。保険診療(体外受精・顕微授精など)との併用が可能です。
妊孕性温存療法では、費用の助成を受けられる可能性もあります。助成を受ける条件には、対象者が43歳未満であること、指定した医療機関で治療を受けること2)などがあります。対象になるかどうかは、治療を受ける予定の医療機関に確認しましょう。
助成内容や費用は、地域によって異なります。お住まいの都道府県に確認するようにしてください。
また、独身の方やがんの治療を優先する方などは、すぐには妊娠を希望しないケースもあるでしょう。保存は1年ごとの更新となり、毎年手続きが必要です。保存期間は、生殖可能な年齢としている医療機関が多く、基準は医療機関によって異なります。
当院での凍結料金は「料金について」を参照ください。
精子凍結のメリット
精子凍結は不妊治療のひとつであり、メリットがいくつかあります。おもなメリットは、ライフイベントの影響を受けにくいこと、将来の妊娠の選択肢を確保できることです。それぞれ詳しく見ていきましょう。
ライフイベントの影響を受けにくい
凍結精子のメリットのひとつは、ライフイベントの影響を受けにくいことです。たとえば、夫が長期の海外出張に行くことになった場合でも不妊治療が可能です。通常であれば、夫が不在の間は、治療を一時中断せざるを得ません。しかし、事前に精子を凍結保存しておけば、凍結した精子を用いて人工授精や体外受精を進められます。
精子凍結は、仕事の都合や予期せぬライフイベントによる治療への影響を防ぎ、計画的な不妊治療をサポートする有効な手段と言えるでしょう。不妊治療を計画的に進めたいカップルにとって、精子凍結は心強い選択肢となります。
将来の妊娠の選択肢を確保できる
精子凍結は、もともと精子の数が少ない、あるいは質が低いと診断されている方にとって、将来の妊娠の選択肢を確保する上で有効な手段です。
精子の質や数は年齢を重ねるにつれて低下する可能性があります。若い時点での精子を凍結保存しておけば、将来の不妊治療で質のよい精子を使うことができます。また、がん治療など、生殖機能に影響を与える可能性のある治療を受ける際にも選択できます。
化学療法や放射線治療などを受ける前に、精子を凍結保存しておけば治療後の不妊治療で使えます。実施にあたっては、生殖医療専門医による十分な説明と、本人(未成年者の場合は本人および親権者)の同意が欠かせません。
精子凍結は、体質的な要因や治療による妊孕性低下のリスクに対し、家族計画を支える重要な役割があると言えます。
精子凍結のデメリット
凍結精子は、ライフイベントの影響を受けにくい、将来の妊娠の選択肢を確保できるメリットがある一方、注意が必要なこともあります。費用と維持管理の手間がかかる、凍結後の精子の質が悪い可能性があるなどです。それぞれ解説します。
費用と維持管理の手間
精子凍結は、費用や維持管理の手間といったデメリットが存在します。精子凍結を行う際には、初期の検査費用や精子を凍結する費用がかかるからです。さらに、凍結した精子を長期間保存するためには、多くの施設で年単位の保管料が発生します。
凍結保存期間は原則1年間としている医療施設が多いです。保存期間の延長を希望する際には、別途更新手続きと費用が必要になるケースも少なくありません。精子凍結は初期費用だけでなく、継続的な費用負担が発生することを理解しておく必要があるでしょう。
また、1年ごとに更新となる施設も多いため、手続きを行う手間も考慮しなければなりません。
凍結後の精子の質が悪い可能性
凍結した精子は一般的に運動率が低下するとされています。そのため、以前は運動精子(活発に動いている精子)が多い場合のみ凍結保存が行われていました。
しかし、顕微授精を実施する場合はひとつの精子で受精可能であるため、この技術が確立してからは、運動精子が少なくても凍結保存が行われることが多くなっています。
また、近年の研究で、新鮮射出精子(凍結しない精子)と凍結融解精子とで生殖補助医療を実施し比較した結果、受精率にわずかな差がみられたものの、継続妊娠率や生児出生率では差がないという報告もあります3)。
上記の内容から、精子の質という観点では、そこまで大きなデメリットはないと考えられます。
おわりに
参考文献
1)日本産科婦人科学会.一般の皆様へ.“不妊治療における精子凍結の費用が変更になります”.日本産婦人科学会ウェブサイト
https://www.jsog.or.jp/news/pdf/20240618_ippan.pdf
2)がん情報サービス.妊孕性.“妊孕性 男性患者とその関係者の方へ”.国立研究開発法人国立がん研究センター
https://ganjoho.jp/public/support/fertility/fertility_02.html?utm_source=chatgpt.com
3)Torra-Massana M, Vassena R, Rodríguez A. Sperm cryopreservation does not affect live birth rate in normozoospermic men: analysis of 7969 oocyte donation cycles. Hum Reprod. 2023;38(3):400-407.
https://academic.oup.com/humrep/article/38/3/400/6994014